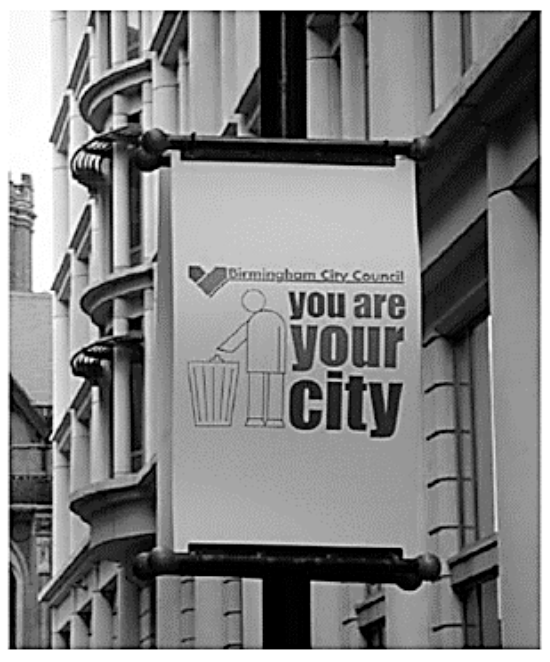7月にプレ・勉強会という形で生まれた、演技とハラスメントの関係を探るプロジェクト『他者の言葉を語る身体のスキャンダル』、「4都市ツアー」無事終了しました。
数年前から、大学の特別講義や、ワークショップをやらせていただくことが増えてきましたが、毎回、お話させていただくたびに、教育の現場こそ、「上演」の最前線なのではないかと感じていた。
始まる前の準備やリハーサル、そして、変わらぬ緊張感。
同じ内容をやっても毎回違う参加者の反応に、時には、即興で内容を変更させてもらったり。
終わりの時間を気にしたり、終わった後に感想をいただいたり。
まさに、「一人芝居」そのもの!
8月末から、京都、東京、長野、大阪と、4都市で開催したワークショップ『他者の言葉を語る身体のスキャンダル』では、渡辺健一郎さんの『自由が上演される。』を参考に、「教育は上演によってのみ可能である」という裏テーマを設定。
講演会やワークショップ、大学での講義などなど、人前に立つ状況において、常にパフォーマーとして「上演」を意識することで、本来受動的な立場に置かれがちな参加者の意識を、「観客」という存在にまで引き上げ、その「上演」に対してより能動的、および「批評的な」姿勢で関わってもらう試みを実施した。
そんなわけで、わたしは、勝手に「4都市ツアー」終えた気になっているのである。
ワークショップを数年続けてみて、これだけは確信を持って言えることがひとつだけある。
それは、ファシリテーター側に発見があることは、参加者側に発見があるということと同じくらい大切なことであるということ。
フランスで演劇教育者国家資格取得のための研修でのオリエンテーションで一番しつこく言われたことは、演劇の教育者が「アーティスト」であり続けることの意義である。
アーティストとして、ワークショップを続けるためには、提供者としてではなく、自分自身が発見と追求の中に身をおく必要がある。
今回、わたしのワークショップ活動を手助けしてくれた『早稲田小劇場どらま館』宮崎晋太郎さんと『うえだ子どもシネマクラブ』直井恵さんには、参加者の存在と同じくらいわたしの活動を大切にしてくださり、わたしにもたくさんの発見があるよう最後まで工夫を凝らしてくれたことに、改めてここで感謝したい。
参加者の皆さんのさまざまな「発言」を栄養に、すくすく成長した今回の企画。
大阪で、最後の「上演」を終えビールを飲んでいると、15歳も年の離れた俳優からSOS。
現場で、主宰の方に伝えたいことが言えず、落ち込んでいる、とのこと。
創作現場に関するワークショップであれこれ持論を並べても、ここでなんのお手伝いができなかったら説得力ないな、と思いながら、彼女が主宰の方にお話をするということで、同席することに。
大概、創作現場で起こる諸々は双方の「気の遣い合い」から、生じていることも多いが、
一番の要因は、本番が迫ってくると、創作現場や稽古後の時間も、演出家はやることがたくさんあって、話し合いなんて無駄な時間はとれないだろうという俳優側の誤解。
いや、実際に、「話し合い」なんてしてる暇があったら、台詞のひとつでも稽古しろやい、という時代遅れの現場もあるのかもしれないが、創作現場において「話し合い」ほどクリエイティブな時間の使い方はない、と声を大にして言いたい。
俳優は、自分の身体という、これほどまでに信用できない道具を使って商売しているのだから、その商売道具が、「迷い」や「不安」で故障してたら、いいパフォーマンスなんてできるわけない。
それは、演出家が一番わかっているから、その「不安」を伝えてもらって、めんどくさがる演出家なんているだろうか。
この夜も、若い俳優の「不安」に、年も倍以上離れた先輩俳優や演出家が真摯に向き合い、とことん時間をとって「話し合い」が行われていた。
わたしは、心底、「クリエイティブ」な時間に立ち会わせていただいているなと感謝した。この時間に立ち会えることこそが、「演劇教育者よ、アーティストであり続けろ!」の言葉が示す真意だな、と。
創作現場で、特に若い俳優たちにこれだけは担保してあげたいことがふたつある。
「交換不可能性」と「尊厳」だ。
「演じる」という行為において、ある意味、誰しもが役を演じる上では「代替可能」である。
キャスティングされた時点では、「代替可能」である「演じる」という行為を、自分以外に「代替不可能」であると体感していくプロセスが稽古とも言えるのかもしれない。
しかし、そもそも、「演じる」という行為が、自身の存在意義や自己肯定感と切り離せていない場合(わたしも含め、こちらのケースがほとんど)、どんなに稽古でうまくいっていても、俳優という仕事から、自身の「交換不可能性」を感じることは非常に難しい。
だからこそ、創作プロセスにおける自身の態度に、俳優としてのプロフェッショナリズムの焦点を合わせ、創作メンバーとの関係性の中に、自身の「交換不可能性」を発見してほしい。
「話し合い」ができればできるほど、あなたの「交換不可能レベル」は上昇していくに違いない。
もうひとつは「尊厳」である。
これは、さまざまな方法で担保できる。
出演に対する対価として、単純に納得できる金額が支払われることなのかもしれないし、
創作チームと長い時間をかけて積み上げてきた信頼関係なのかもしれない。
もしくは、自分の発言にしっかりと耳を傾けてもらえることなのかもしれない。
自分の「尊厳」が何によって担保され、何によって損なわれてしまうのか。
創作現場で、ただただ「不安」に苛まれている時、自身の「交換不可能性」を見出せない時、「尊厳」というキーワードに立ち返ることで見えてくるものは多い。
案外、小さなことだったりするものだ。
La dignité「尊厳」または「品格」という意味のフランス語の名詞である。
これは、私が、母国語ではないフランス語という外国語を使って、演技をする上で、ずっと向き合ってきた言葉である。
どんなに専門的に発音を訓練しても、自分の発している言葉にアクセントは残る。
自分の言語レベルに演技が引っ張られて、どうしても、幼くなってしまう傾向が強かった。
声の響きや、身体のあり方。
自分の完璧ではない言語能力を誤魔化すかのように、無意識のうちに、無駄な「笑顔」をつくっていることもあった。
そんな時、憧れの先輩女優から言われたのが、この言葉、「La dignité」。
「媚びるな、La dignitéを持て!」
子供の頃から、言葉がわからない環境で生活していたことが多く、言語習得時における「プライド崩壊」慣れをしている私でも、あの「子どもにかえったような感覚」は、やはり辛い。
それでも、どんな状況でも、私たちが人間である限り、「尊厳」は絶対に決してなくしてはならない。
周りから笑われようと、そんな小さなことで大袈裟と思われても、「尊厳」は持ち続けなければいけない。
来年も、「上演」としてのワークショップは続いていきます。
演技とハラスメントの関係を探るプロジェクト『他者の言葉を語る身体のスキャンダル』は、創作現場の向上のために、全国どこへでも向かいますので、これからよろしくお願いします。