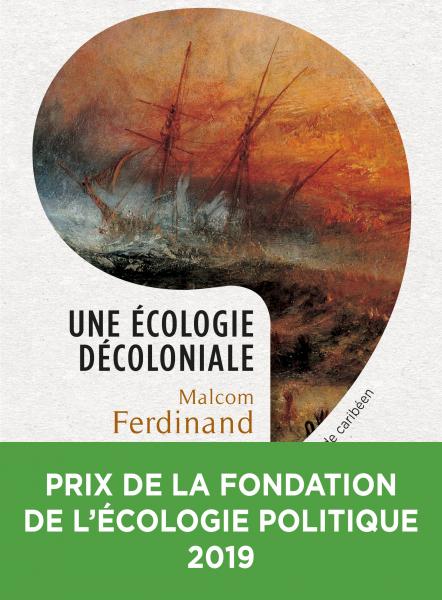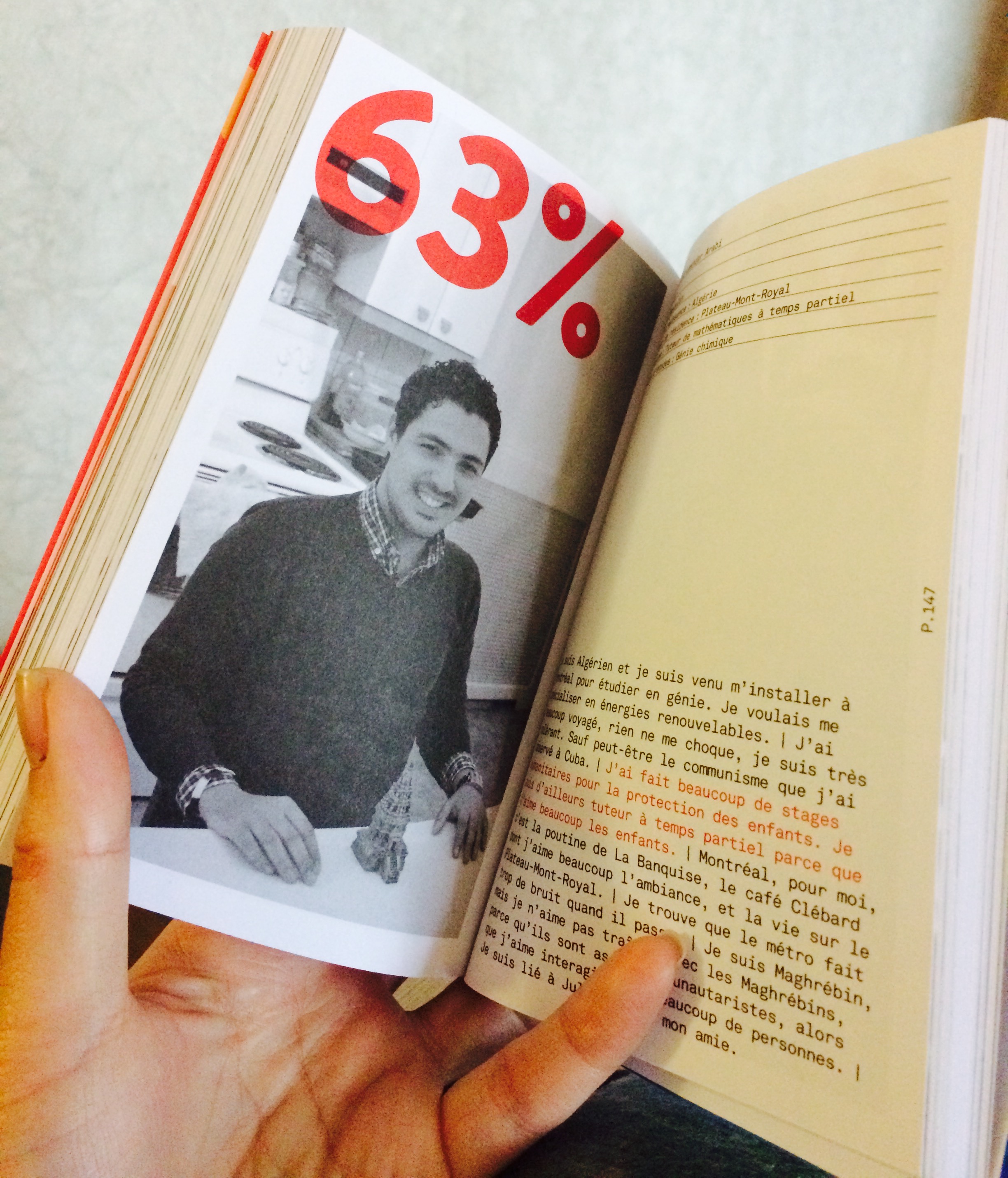毎年モントリオールで開かれている舞台芸術フェスティバルFestival TransAmeriqueの若手アーティスト研修に参加してきました。
(シアターアーツでこのフェスティバルに関して詳しく紹介されています:http://theatrearts.aict-iatc.jp/201610/4837/)
(前ディレクターのインタビュー記事も国際交流基金のページで紹介されています:http://www.performingarts.jp/J/pre_interview/0809/1.html)
この若手アーティスト研修は、世界各国から集まったフランス語圏のアーティストたちによる国際ミーティングの場。
今年は、フランス、ケベック、カナダ、キューバ、ハイチ、イタリア、ドイツ、イラン、ベルギー、メキシコ、スイスから集まった24人のメンバーで11日間を過ごす。
応募条件は25歳から35歳までの舞台芸術に関わる「クリエイター」
年によって、多少ばらつきはあるものの、今年は参加者のほとんどが、演出家、もしくは振付家で自分のカンパニーやアソシエーションを運営する主宰の立場のアーティストがほとんど。
演劇、ダンスに限るという条件はないので、サウンドパフォーマンスや、インスタレーション、美術よりのパフォーマンスと、それぞれの参加者が関わっている分野も多岐にわたる。
そもそも、このフェスティバルのプログラムの特徴が、まさに最近よき聞かれる「マルチディシプリナリー」なものなので、このプログラムに興味を持った人たちも、いい意味でカテゴライズできない場所で活動している人が多かった。
応募締め切りは今年の1月初め。
履歴書とモチベーションレターを提出する。
フェスティバル側とともに財政援助を行う各国の事務局が選考に関わるので、合格の通知がきたのは、1ヶ月以上経ってからだった。
日本に窓口は設けられていないので、私はフランスの選考に応募したのだが、外国人を受け入れているのは、フランスだけで、他の国は、その国の国籍を持つ人が優先して選ばれたようだった。
フランスからは私の他にも、フランス在住5年目のイラン人のアーティストと、リヨンで活動するドイツ人のアーティストが含まれており、やはりフランスの懐の広さを感じずにはいられない。
俳優をメインでやっているのは、私くらいのものだったので、まずは他の参加者の経歴に圧倒されるところから始まり、フランス語を第二言語として使用している参加者たちの言語能力の高さにも打ちのめされ、やはり何年ヨーロッパにいても、この感覚はなかなか消し去ることができないと実感。
プログラムは連日9時から23時まで。
23時からは、もちろんフェスティバルバーでほぼ連日イベントが開催され、睡眠時間はどんどん削られていく。
具体的な活動内容としては、毎晩、フェスティバルのプログラムを観劇し、その作品について、朝から、まずはメンバーのみでの、クリティックを行う。
午後は、主に前日に鑑賞した作品の演出家や振付家が私たちのグループに参加し、ディスカッションが続けられる。
その他には、モントリオールの劇場ディレクターに会ったりと、モントリオールを中心としたケベックの舞台芸術プラットフォームを探っていく。
ケベックという特殊な土地柄もあって、ディスカッションの内容は、政治的な話題がほとんど。
正直、全く自分の社会に対する知識量が追いついていなかった。
連日ぶちあたる壁の量は、ひとつやふたつではない。
そもそも、23人を前に自分の意見をフランス語で理論立てて話すということだけでも、毎回手に汗を握る思いで、この緊張でアドレナリンが出る感じ、なんて演劇的なんだろう!と思っていた。
俳優、演出家という立場にかかわらず、
「批評」というキーワードが、
いかにアーティストを一人前にするかということを痛感する。
「批評」とはつまり、「問題意識」を持つこと。
その「問題意識」こそが、具体的な続ける理由を生み出す。
一言で言ってしまえば、30代という年齢が幕をあけるとき、
夢が、夢のままでは、物足りなくなるのだと想像する。
芸術家というと、なんとなく夢追い人みたいなイメージから逃れにくいのだが、
彼らの熱意と知識量、そして、社会への目の向け方に触れていると、
この人たちが、これから世界を動かしていくんだと信じずにはいられない。
結局はそのフィールドに関わる人たちの姿勢が、
そのフィールドの社会における立場を左右する。
演劇が世の中に必要とされるか、されないかも、
つまりは、演劇に関わっている人たち次第という単純な回路なのではないかと想像する。
それにしても、自分の無知を知り続けるということほど、地獄、かつ、刺激的なことはない。
私がおそらく一番世間知らずだったから、一番得をしたのではないかと自負する。
フランスにきてから、常々実感するのは、
コミュニケーション能力は、筋肉と同じだということ。
筋トレしなければ、育たない。
語彙を豊かにするために、同じレベルの筋トレではなく、
負荷を少しづつあげていく必要がある。
例えば、二、三人の間で、自分の意見を言うことと、数十人の前で意見を言うのとでは、
これまた、全く違う筋肉が求められる。
いつも、ここまで打ちのめされて、体に毒じゃないかと危惧するが、
どこをどうトレーニングしなければいいかわかってさえいれば、あとは時間さえあれば、人間は割とすぐに変われる生き物なのだと思う。したくなくても、ついつい成長してしまうのが、人間。
自分が底辺に位置するであろう場所に身をおくことは、
怖いし、苦しいし、惨めであるに決まっている。
ただ、「そんな屈辱的な場所」で得るスピードとインパクトは超絶である。
だからこそ、気づかないうちに「そんな屈辱的な場所」に入ってしまっていたというのは理想的だ。
しかも、高い確率で、知らない世界に足を踏み入れるという行為は、「そんな屈辱的な場所」に連れて行ってくれる。
そんなわけで、今回も、最高に屈辱的で最高にハッピーな出会い、終了!